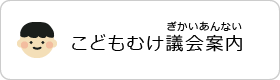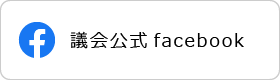にいがた市議会だより
第109号(令和7年4月20日) 5ページ
最終更新日:2025年4月20日
一般質問の要旨
- 一般質問者は22人です。質問は主なものを掲載しています。
- [答]の末尾にかっこ書きの記載がない答弁は、全て市長答弁です。
- 議会の録画中継画面は下の二次元コードからご覧ください。
2月定例会の録画中継は、次回の定例会の録画中継が開始されるまでの間ご覧いただけます。

新市民クラブ 内山 幸紀

本市農業戦略の総括と農業活性化研究センター
[問]本市の農業戦略は、園芸へのシフトではなく「攻めの農業」として新潟コシヒカリや酒米を作り、産学官金の民間主導で加工などを行う出口戦略により、農業者自らが価格決定権を持てる産業にすべきと考えるが所見を伺う。
[答]価格決定権や所得向上に向け、農産物の加工や農家レストランの経営などの6次産業化や食品関連産業との農商工連携を推進していく。
[問]農業活性化研究センターはゲノム編集技術および農産物の品種改良の施設とすべきである。例えば、本市の名産品のル レクチェの生産者を巻き込み、耐病性や多収・秀品率の高い品種改良を進めてはと考えるが、所見を伺う。
[答]ゲノム編集や品種改良は専門的な技術や高額な機材、長期の研究期間を要することから、必要に応じて、国、県、大学との連携を図りながら、産地に寄り添った試験研究を進めていく。
翔政会 美の よしゆき

消防団の人員確保策
[問]政治家は市民の生命を守ることが第一の仕事であり、市は市民が市民を守る仕組みを維持することが大切である。消防団は、普段は別の仕事をしながら、地域防災の支えになる役割を担う消防機関である。消防団の人員確保に向けた入団促進活動に係る回数制限の有無について伺う。
[答]本市では、全班に1名の新規入団を目標とした「一班一人運動」を実施している。この運動は、各班に入団促進担当者2名を指定し、1人当たり年間3回を目安に活動しているが、入団促進活動の回数に上限は設けていない。

消防団員募集のチラシ
翔政会 内山 航

経済成長戦略プランの必要性とみなとまち新潟と水の都
[問]本市には「中小企業・小規模事業者活性化プラン」「企業立地ビジョン」があるが、20政令市中14の政令市は経済分野の最上位計画としての成長戦略プランがある。本市も策定を検討すべきと考えるがいかがか。
[答]総合計画における産業振興の分野別計画は、議員指摘の計画に加えて「新潟県新潟市・聖籠町基本計画」がある。今後も経済団体など関係者の意見を聞きながら経済施策を進めていく。
[問]本市の文化として「みなとまち新潟」と「水の都」を、観光、環境、まちづくり、経済の面からしっかりと認識して発信し、根付かせていくべき。令和7年度の重点事業内容と今後の取り組みの方針について伺う。
[答]川湊や潟の歴史・文化を発信する映像を制作して上映する他、潟体験ツアーを実施するなど、「みなとまち新潟」をアピールしていく。
日本共産党新潟市議会議員団 倉茂 政樹

コメ農家を支えることと児童館の地域格差の解消
[問]主食であるコメは、生命を維持するために必要なカロリーを摂取できる食糧であり、価格を市場原理に任せるべきではない。需給と価格の安定に責任を持ち、ゆとりある需給見通しで生産と備蓄を拡大すべきでは。
[答]県は米の安定供給のため、主食用米の増産目標を掲げるとともに、加工用米など需要に応じた生産を支援するとしている。本市も需給の見通しを踏まえ、米の生産を支援していく。
[問]児童館ガイドラインでは、こどもの居場所として14年も前から児童館が位置付けられ、新たなガイドラインでも強調された。これを契機に児童館のない秋葉区にも設置し、地域格差をなくすべきであると考えるが、所見を伺う。
[答]本市の配置方針で、児童館は既存施設を有効活用するとしており、それぞれの地域ごとに特色を生かした多様な居場所づくりに努める。
日本共産党新潟市議会議員団 鈴木 映

補聴器購入助成の年齢制限撤廃と学校給食時間の確保
[問]高齢者の認知症危険因子として、うつ病や不活動、社会的孤立があるが、補聴器の利用により社会参加の増加など改善効果も認められる。補聴器購入助成は、74歳までが対象だが、認知症予防や高齢者福祉にもつながることからも、年齢の上限を撤廃すべきと考えるがどうか。
[答]加齢による身体機能の低下は聴覚に限らないが、生活の質の確保のため、保健と福祉の連携を高め、総合的に検討していく必要がある。
[問]令和5年10月の学校給食懇話会の提言で、食缶方式による全員給食と十分な給食時間の確保が示された。令和7年度からの全員給食の実現に向け、給食時間の確保はどうなっているか。
[答]懇話会の提言を踏まえて、令和7年度に全員給食化を予定する中学校の多くが、校時表を見直し、喫食を含めた給食全体の時間の確保に向けて検討している。(教育長)
各特別委員会中間報告の要旨
大都市制度・行財政改革調査特別委員会
行財政改革全般についての大都市税財源の在り方で、年収の壁などの引上げの議論における地方自治体の住民税の減収分の取扱いについて、臨時財政対策債で半分を補塡(ほてん)するなどの方法ではなく、国が恒久財源化して補塡することは大都市制度の点において重要と考える。
区の在り方については、政令市でありながら大きく人口が減ってきている状況で、あるべき区の姿については、総合区制度も排除せずに議論すべき。
人口減少対策について、未婚化、晩婚化が少子化の主たる要因で、人口減少を抑制する方策として婚姻件数の維持は重要なファクターだと思うため、結婚を希望する人には、それが早期にかなえられるよう、若者の出会いの場の創出が重要と考える。

農業活性化調査特別委員会
本市の農業を活性化し、広大な農地を維持するために、個人農家をどう誘導するかが課題となっている。農村地域・集落の維持、活性化には、大規模法人だけでは成し得ないと認識し、可能な限り個人農家も頑張れる環境整備が必要となる。
米プラス園芸を推奨してきた県と市の施策も、限界が見えてきていると感じる。稲作だけで継続する方法はないか、そのための生産基盤整備はどのような策が考えられるか、ほ場整備だけではなく、施策の工夫が求められる。
稲作専門の個人農家は特に自身の代で終わりと覚悟を決めているケースが多い傾向にある。後継者が育つための有効な施策など、さまざまな課題に対し、今後も鋭意調査、研究を行っていく。

広域観光交流促進調査特別委員会
本市の観光戦略や中長期のビジョンとゴールが必要である。
観光資源と自然環境、今後予定される開発を洗い出し、戦略と計画を持つべき。本市の観光をどうしていくか、数字を把握し、計画を作り実行していくことが必要。
佐渡島(さど)の金山が世界遺産に認定されたため、今後さらに佐渡市と連携し、本市へ立ち寄る仕組み作りを強力に進めるべき。
地域住民と協力し、芸能文化を観光資源として結び付けることが必要。伝統文化を継承しながら持続可能にするため、稼ぐ視点を持つべき。
観光と環境保護の二項対立ではなく、両立させていくことが必要で、潟や川、海辺の自然環境を生かしていくべき。障がい者や高齢者が気軽に観光できる取り組みが必要である。

地域公共交通調査特別委員会
バス運賃値上げなどについて、新潟交通株式会社より参考人を招致し、バス事業の収支状況などの報告を受け、値上げの必要性について説明を受けた。その後、新潟交通との新たな運行事業協定について、意見を整理し、担当部局に提出した。
新バスターミナル開業を受け、新潟駅から新バスターミナルへの案内や移動の利便性について、委員有志による現地調査を行い、問題点を共有し、担当部局へ改善の要望を提出した。担当部局も取り組みを進め、改善状況について報告を受けた。
これまでの調査研究を踏まえ、今後、バス交通維持のための支援策の追加の必要性、バス運賃均一料金、料金格差などの見直しなどについて、引き続き調査、研究を継続するべきと考える。