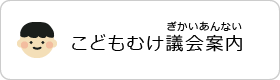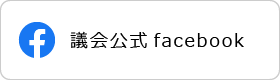にいがた市議会だより
第109号(令和7年4月20日) 3ページ
最終更新日:2025年4月20日
一般質問の要旨
- 一般質問者は22人です。質問は主なものを掲載しています。
- [答]の末尾にかっこ書きの記載がない答弁は、全て市長答弁です。
- 議会の録画中継画面は下の二次元コードからご覧ください。
2月定例会の録画中継は、次回の定例会の録画中継が開始されるまでの間ご覧いただけます。

翔政会 荒井 宏幸

本市経済の発展と避難所運営委員会
[問]にいがた2km圏内への企業誘致により新たな就労の機会が作られているが、若者や女性にとって魅力ある雇用が創出され、人口流出に歯止めはかかっているのか。また、IT企業53社2,200人の雇用が見込まれる中で、正規雇用者の割合は。
[答]新規雇用の若者の割合が8割かつ女性の割合は6割以上で、正規雇用者は求人の約7割である。新卒採用も2割以上のため、若者や女性の転出超過抑制に効果が出ていると考える。
[問]各避難所において避難所運営委員会は必要不可欠であると思っているが、本市全体の立ち上げ率は55.3%である。立ち上げが進まない背景と今後の取り組みについて伺う。
[答]周辺自治会との連携に時間を要しているなどの背景がある。令和7年度は地域の実情に合わせた講習会を行うなど立ち上げ促進を図る。
無所属の会 幸田 健太

無料学習会の会場拡充と消防団員のコンビニ利用
[問]無料学習会は、家庭の経済力の格差を学力格差にしないためにも意義のある事業である。地元に会場のないこどもが、遠距離を理由に参加を諦めないためにも、会場のない秋葉区、南区、西蒲区に会場を設ける考えはあるか。
[答]会場のない区の保護者から、居住区にあれば参加させたいとの意見が一定数ある。学習会の開催は、会場や学習支援員の確保など体制を整える必要があるが、学校の長期休暇などを利用した試行的な開催について検討する。
[問]地元の出初め式に参加した際に、消防団員は活動服を着用してコンビニでの商品購入やトイレの利用が禁止されていると聞いた。消防団員が、ポンプ車や活動服でのコンビニを利用することは禁止されているのか。
[答]これまで消防団員に対して、適切な利用を注意喚起しているが、禁止はしていない。
新潟市公明党 松下 和子

デジタル地域通貨の導入とGIGAスクール端末の更新
[問]デジタル地域通貨は地域を限定して利用できる上、健康ポイントや自治会への加入、運転免許証の自主返納など、地域活性化の切り札にもなる。市民にとってもプラスとなる新潟市らしい地域通貨の導入をしてはどうか。
[答]実現したい地域社会の姿を議論し、持続可能なシステムを構築できれば、地域経済やコミュニティの活性化に活用できることから、庁内横断的に導入の可能性を考える。
[問]GIGAスクール端末の処分委託やデータ消去が適切に行われなかったため、個人データが流出するなど不適切な事案が各地で相次いでいる。端末の更新に当たりデータ消去などが適正に処理されているか確認をすべきでは。
[答]データ漏えい防止のため賃貸借契約の中で記録媒体などを物理的に破壊し、廃棄証明書を提出することとしている。(教育長)
翔政会 伊藤 健太郎

本市の特長を生かすための行財政改革と児童館・児童センター
[問]本市を選ばれる都市にするためには、本市独自の課題を解決し、強みに一層磨きをかける施策を講じるための人員と予算が必要である。そのためにも、不断の行財政改革が必要だと考えるが所見を伺う。
[答]前例にとらわれず、時代に即した業務の見直しや民間活力の導入、財政基盤の強化など経営資源の適正配分に向けた取り組みを進めることで、持続可能な行財政運営を推進していく。
[問]財産経営推進計画では、老朽化した児童館や児童センターは廃止するとしているが、少子化対策や子育て支援充実のためにも、子育て支援施設としての再編を検討するなど、方針を改めるべきと考えるがどうか。
[答]実際の機能移転の検討に当たっては、施設の配置状況が地域によって異なることから、地域の皆さまの意見を聞き丁寧に進めていく。
翔政会 東村 里恵子

新津鉄道資料館の鉄道コンテンツの活用
[問]新津鉄道資料館の展示内容は、国鉄時代の収蔵品やミニSLといった動態展示まで幅広く、さまざまな来館者に対応できるレベルである。「鉄道のまち・にいつ」の歴史に触れ、地域を知ってもらうという意味でも、来館者を増やすことは非常に重要で本市の活性化にもつながると考えるが、来館者を増やす取り組みを伺う。
[答]リニューアル10周年を契機に、令和7年3月末に電車運転シミュレーターを更新する予定。新潟ならではの路線を運転体験できる唯一の設備で、鉄道ファンや家族連れの来館を期待する他、海外からの誘客にも取り組む。

新しい電車運転シミュレーター
新風にいがた 小林 裕史

高齢者あんしん連絡システムと新潟市民病院の財政課題
[問]単身高齢者などは、支援ニーズが適切に把握されにくく、緊急時の支援者がいない場合も多い。高齢者あんしん連絡システム事業は、在宅の単身高齢者が緊急時に24時間体制の受信センターに通報できる装置を貸与する事業であり、今後重要度は増していくと考えるが現状は。
[答]利用者数は減少傾向だが、住み慣れた地域で安心して生活するための重要な事業であり、必要な方が利用しやすい環境整備に努める。
[問]新潟市民病院事業運営審議会の助言を、経営改善に向けた実効性のある取り組みにつなげるとともに、外部コンサルタントを導入した会議体の設置が必要だと考えるがいかがか。
[答]急激な資金の減少が見込まれる中、可能な限り経営改善を進める必要があると認識しており、外部の専門家の意見を聞くことも視野に入れながら具体化を進めていく。(病院事業管理者)
新風にいがた 野口 光晃

賃貸型応急住宅の入居期間延長と高校のタブレット端末の無償化
[問]能登半島地震の被災者に民間賃貸住宅を応急住宅として提供する制度の入居期間は2年だが、地盤が安定していない状況から、今後の居住について判断できない人が多くいる。被災者の状況に応じて入居期間を延長すべきでは。
[答]延長が認められるのは真にやむを得ないケースに限られ、要件に合わない場合は市営住宅入居の案内など、寄り添った対応を行う。
[問]教育現場におけるタブレット端末費用について、自治体によって公費負担とするか保護者負担とするか方針が大きく異なる。現在、市立高校は無償であり、今後も公費負担を継続すべきと考えるがいかがか。
[答]市立高校のタブレット端末は令和9年度に更新予定だが、国に対してさらなる財政措置の拡充を要望するとともに、国財源を活用した公費負担での整備について検討していく。(教育長)
新潟市公明党 志賀 泰雄

放課後児童クラブ運営指針改正と私道等整備助成金の積極活用
[問]放課後児童クラブの運営指針改正により、こどもの権利についての学習と、こどもの意見を受け止める体制、生活や遊びについて共に考え、決めるよう示されているが、クラブでは具体的にどのように対応するのか。
[答]クラブ支援員が自ら進んでこどもの権利について学習するため、研修の受講などを促進するとともに、クラブ運営にこどもの意見を反映する取り組みを一層強化していく。
[問]私道の補修や整備に対応するため、補助率が2分の1の私道等整備助成金制度があるが、あまり活用されていないと考える。活用目標を設定するなど、もっと積極的に制度の活用を進めていく必要があるのではないか。
[答]私道の利用形態は地域により異なっているため、住民の安心と生活環境の向上に寄与するよう助成制度の見直しを検討していく。