学校給食の歴史
最終更新日:2025年10月10日
学校給食の歴史
学校給食は、栄養のバランスのとれた食事の大切さを理解し、食生活の大切さを身に付け、日常の生活に生かすことができる能力や態度を育てることを目標にしています。
また、食事マナーへの理解を含め、みんなで一緒に楽しく「食べる」体験を通して、望ましい食習慣と人間関係を育てるなど、体と心を育てる健康教育の一環として重要な役割を果たしています。
新潟市では、1947年(昭和22年)1月20日に学校給食が開始されました。
ここでは、新潟市の学校給食が始まってから現在に至るまでの歴史について写真を交えながら簡単にご紹介します。
おことわり
平成18年以前の状況については、平成17年3月21日の合併前の旧新潟市の状況を中心にご紹介しています。
昭和40年頃の学校給食
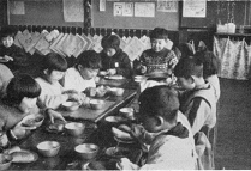
ある日の給食メニューは・・・コッペパン、ミルク(脱脂粉乳)鯨のこはく揚げ、野菜カレー炒め
現在の学校給食

ある日の給食メニューは・・・ごはん、ゆかりふりかけ、ワンタンスープ、お豆とかぼちゃのコロッケ、風味漬け、牛乳
学校給食年表
| 年度 | 新潟市 | 国 |
|---|---|---|
| 明治22年 | 山形県鶴岡市の私立忠愛小学校で学校給食を開始 |
|
| 昭和22年1月 | みそ汁中心の補食給食を開始 (旧軍隊所有の鮭・あさり味付け缶を26国民学校へ配布したのが最初) |
全国都市の児童300万人に対して学校給食を開始する。 |
| 「みそ汁+脱脂粉乳のミルク」の給食を開始(写真1、2) | ||
| 昭和24年 | ユニセフ給食が開始され、健康状態を研究する研究指定校の1つに沼垂小学校が選ばれる。 | |
| 昭和25年 | 「パン+脱脂粉乳のミルク+おかず」の完全給食開始(写真3) | 8大都市の小学校児童に対し、米国寄贈の小麦粉を使って、初めての完全給食が開始される。 |
| 昭和27年 | 日本学校給食会が脱脂粉乳の輸入業務を開始。また、ユニセフ寄贈の脱脂粉乳の受入配分業務も実施される。 | |
| 昭和29年 | 「学校給食法」が成立・公布 |
|
| 昭和32年 | 学校給食10周年記念行事開催 | |
| 昭和38年 | 学校給食未実施校に委託混合乳(牛乳60ccに20gの脱脂粉乳を溶かしたミルクを混入・ビン装)が開始(写真4) | ミルク給食の全面実施が推進される |
| 昭和44年 | 主食にソフト麺導入(写真5) | |
| 昭和47年 | 混合乳から牛乳へ切り替え(写真6) | |
| 昭和49年4月 | 学校給食用物資の共同購入方式を導入。 共同献立・共同購入が開始される |
|
| 昭和51年 | 学校給食に米飯が正式に導入される。 |
|
| 昭和52年 | 米飯給食開始(12校で月1程度) | |
| 昭和57年 | 米飯給食完全給食校(園)で週1回実施(写真7) | |
| 昭和63年 | 米飯給食:完全給食校(園)で週2.5回実施 |
|
| 平成4年 | 米飯給食:完全給食校で週3回実施 |
|
| 平成9年 | 「学校給食衛生管理の基準」が定められる | |
| 平成12年 | ステンレス・ポリプロピレン複合食器の「茶わん」を使用 | |
| 平成15年 | 給食未実施中学校26校において、「新潟市中学校スクールランチ」が開始(写真8) |
|
| 平成17年 | 栄養教諭制度開始 |
|
| 平成19年 | 「新潟市食育推進条例」が制定される | |
| 平成20年 | 東、中央、西、西蒲区にて完全米飯給食を実施 |
「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」が日本学校保健会から示される。 |
| 平成21年 | 北・江南・秋葉・南区において完全米飯給食を実施 |
「学校給食法」一部改正 |
| 平成22年 | 日本APEC新潟食料安全保障担当大臣会合開催に合わせ、参加国の代表的な料理をAPEC給食として実施 | |
| 平成27年 | 自校式給食校においてポリプロピレン製の食器から耐熱ABS製の食器に順次入替え開始 | 「学校給食における食物アレルギー対応指針」が文科省から発行 |
| 平成28年 | G7新潟農業大臣会合開催に合わせ、7か国の料理をサミット給食として実施 |
|
| 平成30年 | 新潟開港150周年を記念し新潟港開港に関連する料理を献立にした給食を実施 | |
| 平成31年 | G20新潟農業大臣会合開催に合わせ、参加国の料理をサミット給食として実施 | |
| 令和4年 | 自校式、センター式給食校においてポリプロピレン製の食器を耐熱ABS製食器、PEN製食器に入替 | |
| 令和5年 | G7新潟財務大臣・中央銀行総裁会議に合わせ、7か国の料理をサミット給食として実施 | |
| 令和7年 | 「新潟市立学校園 食物アレルギー対応マニュアル」発行 |

昭和20年代の学校給食

昭和20年代学校給食の様子

昭和20年代学校給食の様子

昭和30年代学校給食の様子

昭和40年代ソフトめん導入

昭和47年牛乳に切り替え

昭和50年代米飯給食開始

中学校スクールランチの様子
28の中学校を食缶方式による全員給食へ切り替え
現在の給食
このページの作成担当
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル4階)
電話:025-226-3206 FAX:025-226-0034

 閉じる
閉じる